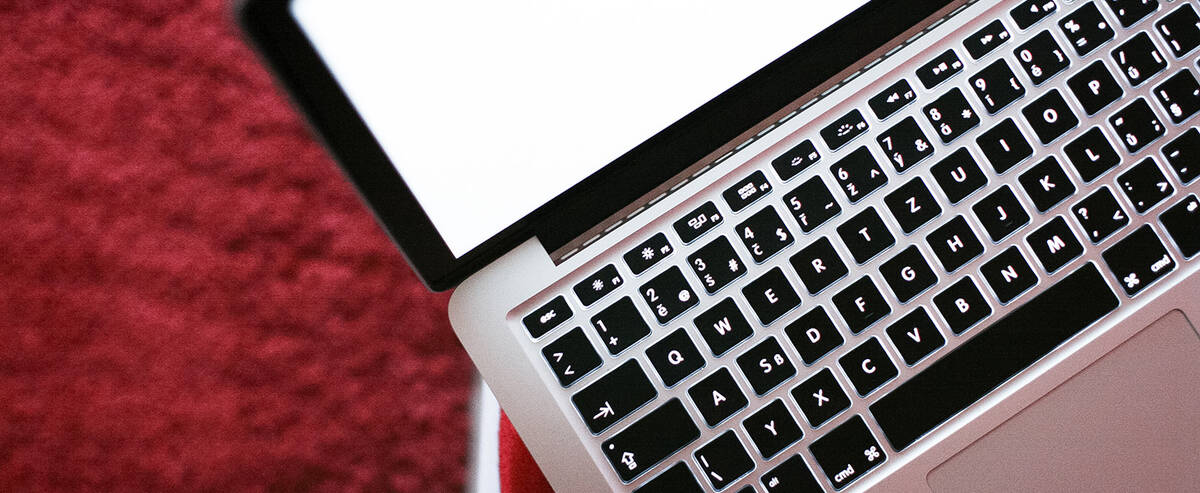子テーマのすすめ
WordPressでサイトを構築しましょう。
ということになってまず最初に考えるのが「テーマはどうするか」かと思います。
特殊な事情でもない限り、選択肢は以下になるでしょう。
- 既存の配布テーマから要件にあったものを探す
- 自分でテーマを作成する
テーマ作成の経験があまりないなら1、充分にあるなら2になるのが一般的かと思いますが、状況や求められる仕様・条件によっては使い慣れた自作テーマがあっても1が視野に入る場合もあります。
どちらが正解ということはないと思います。
配布テーマを使うなら
世界的に利用者の多いWordpress界隈では無料・有料問わず数多くのテーマが配布されています。
特に有料テーマの中には、非常に高機能でハイクオリティなデザインパターンを用意しているものがあり、これならどんなサイトだって作れるのでは?というものもたくさんあります。
もしゼロイチで作ったらとんでもない工数がかかりそうな機能があっという間に実装できるのは魅力的です。
有料テーマの中には有料プラグインがバンドルされているものもあります。
年間7,000円前後の支払いが必要なプラグインがバンドルされているものもあり、これが買い切り7,000円で購入できるのであればかなりお得です。そのプラグイン目的で購入を考えてしまう場合もありそうです。
注意点としては、そのテーマがいつまでアップデートされるのかわからない、という点です。
テーマのアップデートが滞るとバンドルされているプラグインの更新も滞ることになります。
プラグインのアップデートができないとのは致命的なリスクになり得ます。危険度の高いセキュリティホールが見つかったとしても修正版にアップデートすることができないからです。
だからといってプラグインの利用を停止したり、別の似た機能をもつプラグインにのりかえることは特にクライアントワークでは不可能です。その場合はバンドルされた有料プラグインの正規版ライセンスを追加購入せざるを得なくなります。
また高機能な有料テーマは、高機能ゆえに使いこなすのには多くの時間、基本的な知識、絶対に使いこなすんだという意欲が要求されがちです。クライアントにそれを要求するのはまず不可能なため、より丁寧なサポート、マニュアルの整備が必要になりそうです。
配布テーマを使う場合には、これらのリスクについてしっかり調査したうえで使うかどうか判断することが求められます。
使うと判断したのであれば、『配布テーマ=親テーマ』『カスタマイズ=子テーマ』と切り分けて運用すべきです。
これにより、配布テーマのアップデートをしっかり適用しながら保守していくことが可能になります。
自作テーマを使うなら
WordPressを使ったサイト構築では、想定外のエラーに対応できるかどうか、何ができて何ができないか、等についてしっかり把握していることが何より大事になります。
そういう点においては、自身にとって「ちょうどいい」自作テーマがあることは何よりの強みになります。
Labridではこの10年ほどオリジナルテーマにコツコツとブラッシュアップを重ね、使いやすいテーマを育ててきました。
そんな弊社のテーマの育成テーマは下記の通りです。
- 読み込みスピードの優先度を高く
- ブロックエディタをより使いやすく
- 子テーマにちゃんと対応
- 特定のプラグインに依存しない
それぞれ掘り下げたいところですがそれはまたの機会として、今回は子テーマを使うことの有用性についてご説明します。
ブラッシュアップを積み重ねること
上でも述べたように、テーマは常にブラッシュアップしていくことが肝要です。
WordPressはもちろん、HTML、CSS/SASS、JSも常に発展しており、それに合わせてテーマを刷新していかないとあっという間に過去の遺物臭が匂ってきます。
自分にとって使いやすさとは何なのか、という哲学じみた考えを反映させることも大事だったりします。
このブラッシュアップは、多種多様な仕様やデザインを実装するなかで「こうした方がもっとスマート」「後で修正しやすいようにこうしよう」「このCSSはこの書き方の方がいいのでは」など、業務での必要に応じたカスタマイズです。
幸いなことにいろいろなタイプのWordpress案件を経験させていただき、多くの改善を積み重ねることができました。
これまでは元となる汎用テーマを案件ごとに直接カスタマイズしてきたので、施した改善を元のテーマに反映させるのを忘れてしまったり、反映させるべきかどうか迷った末に反映させなかった結果、後で後悔することもありました。
またブラッシュアップするたびに、元テーマから派生した様々な案件別テーマに改善内容を反映させることは難しいため、案件に携わった時期によってテーマ仕様が変わっていて自分でも混乱することがたびたびありました。
今になって思います。自作テーマはカスタマイズ元として作った骨組みテーマなのだから、ややこしい上書きルールの存在する子テーマを使わなくてもいいよね、というのは間違いであったと。そういうテーマこそ、子テーマでカスタマイズ部分を切り離すことで永続的にアップデートできるようにしておくべきだっと。
子テーマを使おう
親テーマと子テーマについてAIに聞いてみたところ、下記のような回答が帰ってきました。
WordPressで親テーマと子テーマを組み合わせると、親テーマのデザインや機能を基にしながら、親テーマのアップデートに影響されずに安全にカスタマイズを加えられます。親テーマが「土台となるデザイン全体」であるのに対し、子テーマは「その土台に上乗せして特定の変更を加えるためのテーマ」です。子テーマを使うことで、カスタマイズ内容が親テーマのアップデートで消えるリスクを防ぎ、トラブル発生時には親テーマに切り戻して原因を特定しやすくするというメリットがあります。
私も幾度か使用経験があります。主に配布テーマを親テーマとして子テーマでカスタマイズする、という使い方です。
引用にもあるようにカスタマイズ内容が親テーマのアップデートが消えないのがメリットなのですが、実際に親テーマにアップデートがあったからと言って公開中の案件の親テーマを上書きできるかと言ったら、怖くてできないのが現実です。親テーマの変更の影響範囲が不明なので、想定外のレイアウト崩れや適用したCSSが無効化されるなどの不具合が発生する確率がないとは言い切れないからです。
配布テーマではそうですが、自作テーマではどうでしょう?
全ては作者である自身のコントロール下にあります。自作テーマでこそ子テーマを最も有効に活用できるはずです。
ただ、何も考えずに今まで使っていた汎用テーマをすぐに親テーマにできるかといえばそう単純でもありません。
何を親テーマで一括管理して、何を子テーマでカスタマイズするのか、という点はしっかり考えて設計しないと子テーマを使うことによってただ面倒が増えるだけだったりします。
子テーマのカスタマイズは、親テーマの改善を視野に入れながらの作業になります。
子テーマに施したカスタマイズを子テーマだけのカスタマイズとするのか、親テーマに吸収して今後の案件にも活かしていくのか、それを常に考えながらの作業になります。切り分けをしやすい設計としておく必要があります。
単純なテーマ開発よりも頭も時間も使いますが、積み重ねたブラッシュアップは今後必ず役に立ちますし、親テーマと子テーマを切り分けたサイト構築は、継続的な保守を行う上で大きなメリットがあります。
具体的にどうやって子テーマを作成するのが効率的か、子テーマの親テーマに対する上書きルールはどうなっているのか、についてはまた別の記事で触れたいと思います。